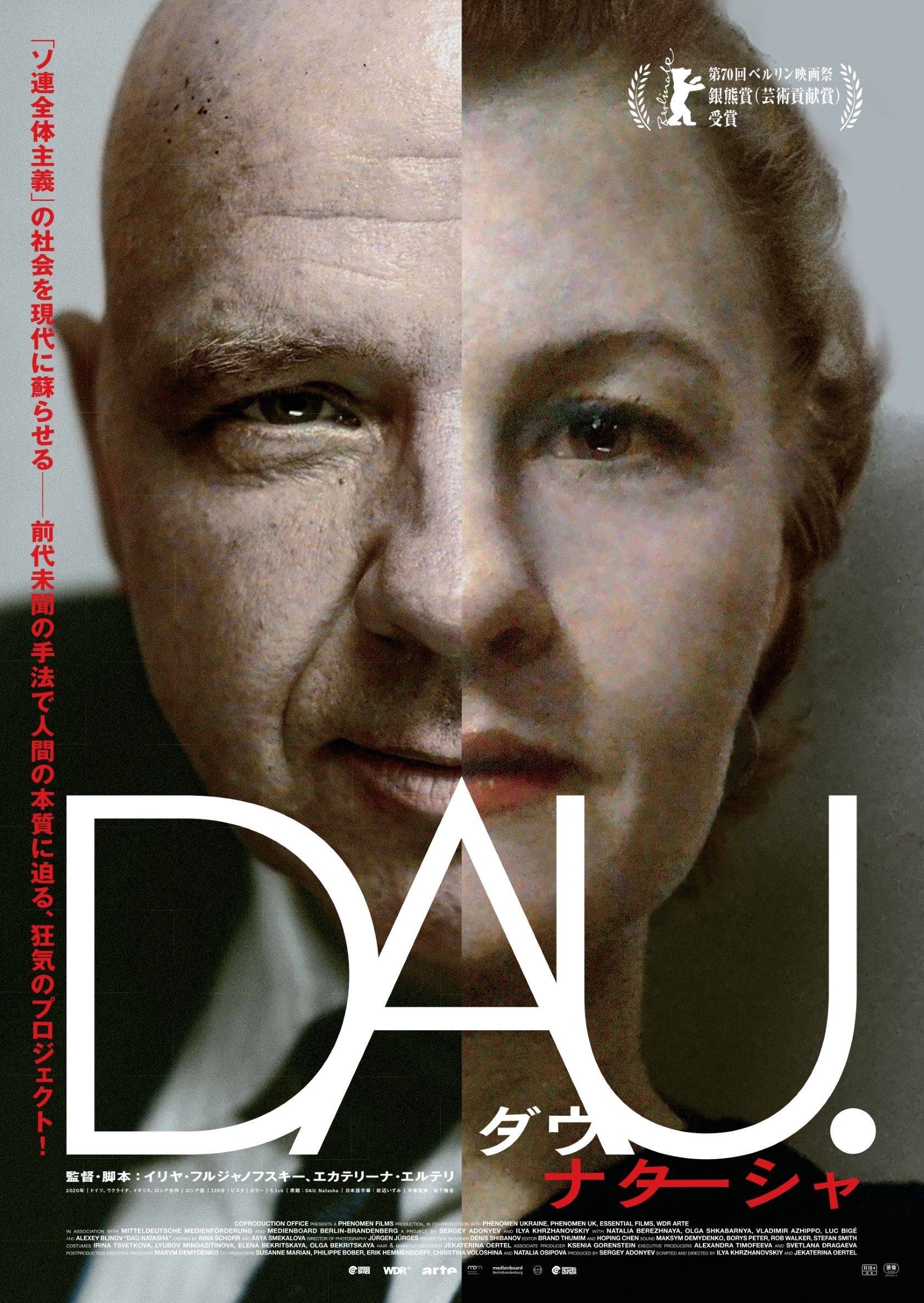『ゆめのまにまに』(2022)-Kaori Harimoto

映画『ゆめのまにまに』
菊地健雄監督作『ハローグッバイ』、瀬々敬久監督作『最低。』、越川道夫監督作『二十六夜待ち』、岨手由貴子監督作『あのこは貴族』、万田邦敏監督作『愛のまなざしを』 などで助監督として参加した張元香織監督。2018年には、映画『船長さんのかわいい奥さん』で長編での初監督デビューも果たしている。そんな張元監督の長編第二作目となる『ゆめのまにまに』が11月12日に公開された。なお本作は俳優や音楽家のマネージメント会社・ディケイド設立30周年記念映画として製作されている。
舞台は、東京の浅草に実在する古物店「東京蛍堂」。そこを行き来するひとびと、モノ、時間、そしてこころが交差する。主演のマコトを務めたのは、「メンズノンノ」専属モデルとしてデビュー後、俳優やフォーク・バンド 「酔蕩天使」のリードボーカルとしても活躍する、こだまたいち。マコトがアルバイトとして働く「東京蛍堂」の店主を村上淳が、店主に逢うために「東京蛍堂」をなんども訪れる真悠子役を千國めぐみが務めた。さらに三浦誠己、山本浩司、中村優子など、ディケイドを代表する素晴らしい俳優陣が脇を固めている。
あらすじ
東京・浅草六区に佇む古物店「東京蛍堂」。
そこでアルバイトとして働くマコトは、店主の和郎に代わり毎日店番をしていた。コロナ禍によりひとびとがマスク生活を強いられるなか、「東京蛍堂」には毎日誰かが訪れる。ある日、そこへ真悠子がやってくる。真悠子はどうやら店主に逢いたいようだが、なにやら訳ありな様子。毎日店へ訪れるそんな彼女をマコトは気になりはじめる……。
作品評論
現実とリンクするリアルな設定と場所
冒頭飛び込んでくるのが、バスに揺られてなにやらノートに書き込みながら東京へとやってくる真悠子の姿。その口元にはマスクが着けられている。そこであーね、と気付く。今の東京なんだねと。リアルな世界では、間もなくやってくるとされる新型コロナウイルス感染拡大第八波にいい加減ウンザリしながらも、ひとびとは少しずつ新しい世界を生きはじめている。ただただ感染を恐れて閉じこもることをやめて、友人と食事に出掛けたり、ライブを楽しんだり、帰省をしたり、ひとによっては海外旅行にも。もちろん口元にはマスクを着けて、あるいはワクチンを接種してだが。
そして実在する「東京蛍堂」という舞台。このふたつがそろえば、それはもう映画か?現実か?という設定なのだ。そしてなにより本作の「派手」な事件や出来事が起こらないところがよりリアリティを感じさせ、わたしのこころをグッと掴んだ。映画は世の中を写す。その時代、その場所、そこで暮らすひとびとのこころを。そしてその時代の匂いが感じられた時点で、わたしにとっては大好物なのだ。
こんなにも歴史的な地球規模の変化があった新型コロナ時代。まさにその現在地に立っているわれわれなのに、なぜかマスク映画は少ない。それは映画の中の世界がひとびとにとって「夢」や「希望」の場所でなければならないからか?それとも見映えの悪さからか?もし後者であったとしたら、言ってやりたい。その見映えの悪い世界にわたしたちは生きているんだと。わたしたちは、それに恥じることもないし、医療従事者をはじめ多くのひとびとが今もなお立派に闘っている。そしてもちろん、本作に出てくるひとびともだ。だからこの作品のようなマスクを着けたひとびとの「派手」な事件や出来事が起こらないこの設定は、わたしたちの生活そのものなのである。不恰好かもしれないけれど、それでもただ生きている。誰かを守り、自分を守るために。そんな等身大の登場人物の姿から考えさせられることは、もはや無限。このリアリティは、監督の脚本・演出はもちろん、役者の演技が素晴らしいからなせる技。ゆったりと流れる川のようなテンポ感が心地よく、鑑賞者を自由にさせてくれる余白を持つ、わたしたちの生活に寄り添っていることが本作の最大の魅力であるとわたしは思う。
マコトという人物像
マコトくん、好き。こういうひとに出逢いたいし、こういうひとになりたいとさえ思った。
しかし作中ではマコトという人物像について直接説明する描写は少ない。唯一女子高生がサクッと語る場面があるが、あとはマコトの言葉や行動から彼の人となりを想像するしかないのだ。まあ、これこそがマコトの魅力そのもので、「そういうとこだぞ!マコトくん」なのだ。そんな自分を語らない「そういうとこだぞ!マコトくん」は、たくさんの素敵な言葉をさらりと零す。なんというのだろう?親でもなく、先生でもない、友人でもないし、兄妹でもない……。祖先?天使?の言葉のような、ほどよい距離感とやさしい空気感が「東京蛍堂」を訪れるひとびとをそっと包み込んでいるのだ。そしてそれは鑑賞するわたしをも包み込む地味にすごいパワーを持っている。
善悪、好き嫌い、正解も不正解もどうでもよくて。このギスギスした世の中において、マコトのようなひとはまさにオアシスであり、ゆめと現実をつなぐ天使なのかもしれない。そのゆったりと流れる川のような囁きに、草臥れたこころがふっと掬い上げられる気がした。
個人的には真悠子に最後に掛けた言葉が大好きで、それこそがマコトという人間を映すひとことであると思う。
幻のラブストーリー ※ここから少々ネタバレ含みます
真悠子は店主の和郎に逢うために、あるいは逢わないために「東京蛍堂」を訪れるわけだが、そのふたりの関係の真意については最後まではっきりと描かれない。和郎は実在するのか?さえ謎のままなのだ。
誰かのもとからやってきて、誰かのもとへとモノを繋ぐ「東京蛍堂」。それはここに訪れるひとも同じことで、真悠子にとっての和郎への想いがまさにソレだったのだろうか。
冒頭の真悠子のノートから、彼女が和郎との関係になにかしらの区切りをつけたいと思っていることはうかがえるのだが、それがどういう状況から、どうしてそうしたいのかはわからない。真悠子にとってはラブストーリーであることは確かなのだが、それは当事者ふたりだけのもの(もしかしたら真悠子だけかもしれないが)であって、登場人物もわたしたち鑑賞者もそれを無理矢理こじ開けて覗こうとはしない。これもリアリティの仕掛けで、実際の世界では無数に起こっている現実。わたしたちはこうやってひととのつながりも、そして恋もまた「まにまに」がちょうどいい。
ゆめなのか、幻なのか、あるいは現実なのか。そのこたえはわからない。ただラストの真悠子の晴れやかな表情が、彼女のこころにひとつの区切りがついたことを明確に物語っていた。
いつかはなくなってしまう儚さ
古物店「東京蛍堂」という舞台、そして今という時代。ひともモノも出逢い別れ、繋がれていく。いつか自分の手元から離れてしまうかもしれない、いつかこの世界からなくなってしまうかもしれない。だからわたしたちはその出逢いを大切に、その瞬間を大切にしなければならない。それがこの世界を創っている。
本作はそんな当たり前であるが、ひとびとが忘れかけていることをあらためて教えてくれる。なんども観てそのときの自分のこころと重ね、さまざまな想像を楽しむのもいいだろう。あるいはコロナが遠い過去の話になったとき、また再見してみるのも楽しみな作品だ。
作品情報

『ゆめのまにまに』ディケイド設立30周年記念映画
2022年11月12日(土)より東京・ユーロスペース他、全国順次公開
監督・脚本:張元香織
キャスト:こだまたいち、千國めぐみ、遊屋慎太郎、野口千優、澁谷麻美、北澤浩志郎、岩谷健司、内藤正記、松浦祐也、和田光沙、玉りんど、藤井千帆、岡部ひろき、浦山佳樹、泉拓磨、高橋綾沙、藤入鹿、原風音、三浦誠己、山本浩司、中村優子、村上淳
エンディング曲:酔蕩天使「サンローゼ」(HILLS RECORDS)
企画:佐伯真吾 撮影監督:山崎 裕
音楽:磯田健一郎 録音:森英司 美術:櫻井啓介 編集:菊井貴繁
サウンドデザイン:弥栄裕樹
ヘアメイク:寺沢ルミ
助監督:二宮崇
製作担当:金子堅太郎
スチール:横山創大
特別協力:浅草・東京蛍堂
文化庁「ARTS for the future!」補助対象事業
スペック:101分/16:9(1.78:1)/5.1ch/2K/カラー/2022
配給:スールキートス
製作:ディケイド
宣伝:フリーストーン
(C) 2022 ディケイド